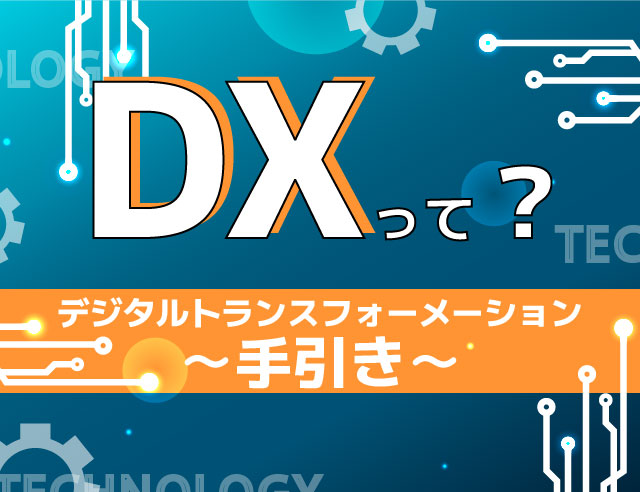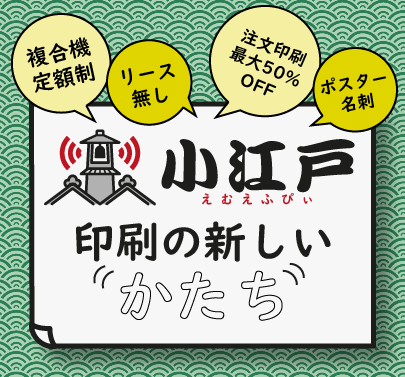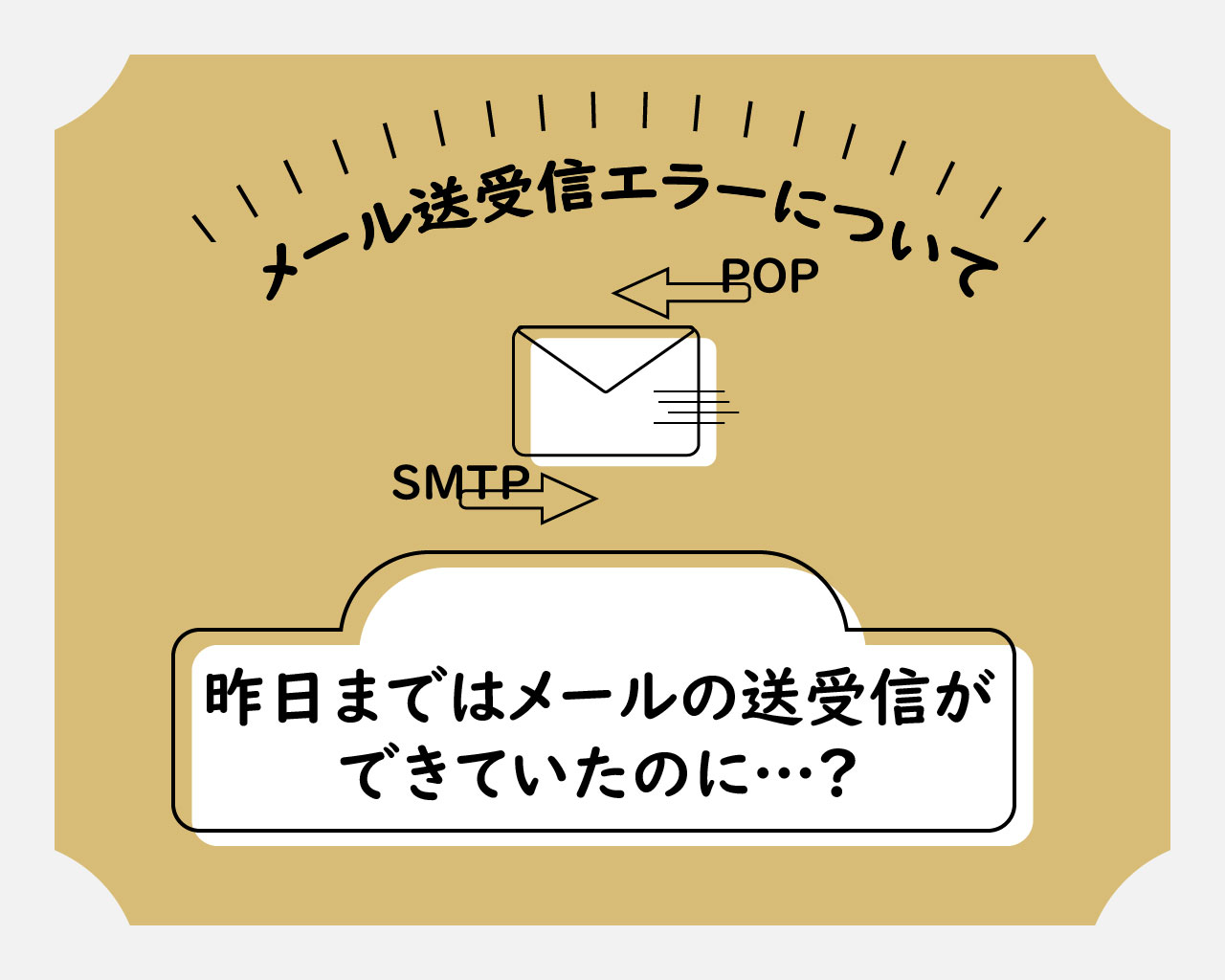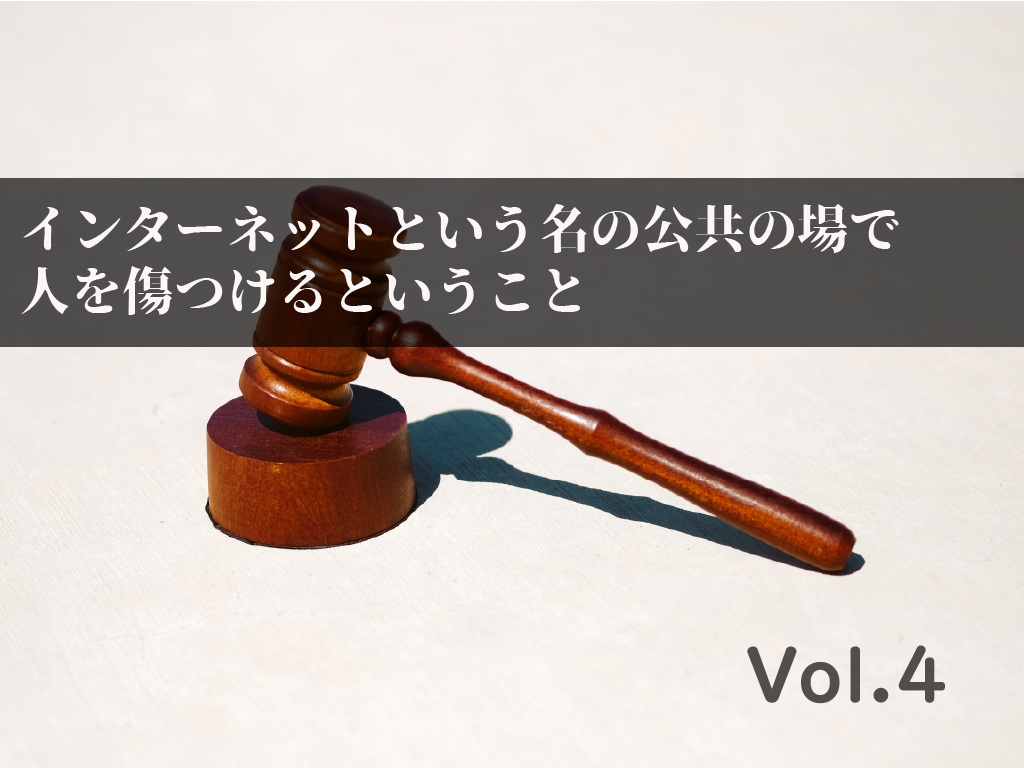おはようございます。小江戸情報セキュリティ相談センターです。
突然ですが、みなさんは初めて切符を買った日を覚えていますか?
わたしは小学二年生の遠足の時、はじめて自分で切符を買って電車に乗る経験をしました。(田舎出身なので…)
では、最後に切符を買った日は?覚えていますか?
自動改札が当たり前になり、ICカードでの乗車が当たり前になり、切符を買う機会はめっきり減ったのではないでしょうか。
今や新幹線の予約すらネット上で可能になり、券売機に並ぶ列を見ることも少なくなりました。
切符の購入に特に難しいことはありません。お金を入れてボタンを押すだけのことです。小学二年生でもできます。
しかし、交通ICカードおよびモバイルICカードの普及で、電車の利用は以前より便利でスムーズになりました。
デジタル化よって人々の生活は便利で豊かなものへとみるみるうちに進化していきます。
IT技術の浸透で人々の生活を豊かにすることをDXと言います。
「DX」この言葉、ご存じですか?デラックスではありません。
デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)です。
本日は、今推進されているDX、「デジタルによる変化・変革」についてお話しします。
DXって?

現代において、あらゆるもののデジタル化は当たり前のことになっています。いつどこでなにがデジタル化、オンライン化してもおかしくありません。
先に挙げましたモバイルICカード、ファストフード店のモバイルオーダー、授業のオンライン化。大型デジタルサイネージなんかも話題になりましたよね。
美容院でも、雑誌ではなく複数の雑誌が収録されたタブレット端末が渡されるようになりました。
あらゆる企業で、勤務管理や販売管理はソフトウェアを用いて行われます。導入直後こそ戸惑ったかもしれませんが、慣れてしまえばアナログ的手法と比べはるかに便利で効率が良くなったのではないでしょうか。企業だけでなく、学校の出席もインターネットやカードを利用して記録されることが増えました。点呼し記帳する時間を省けば、その分授業をする時間が増えます。
デジタル化することによる利点が、変化に適応しなければならない億劫さに勝る時代です。
現代の若い方はデジタルやインターネットが当たり前の世代ではありますが、現代ではもう「デジタルでスマート」という言葉は若者の特権ではないのです。
そうして次から次へとデジタル化が進み、より便利でより効率よくなっていく・・・それこそがDX、というわけでもないんです。同じようなものではありますが、DXはより社会に影響を与えるものでなければいけません。
経済産業省が発表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、DXは次のように定義されます。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」(引用元:経済産業省HP)
商品やサービスをデジタル化によって変化させるのではなく、それによって業務そのもの、企業文化・風土といった環境を変革していくことこそがDXなのです。
デジタル化によって業務そのものや企業文化を改変し、競争上の優位性を確立、つまり企業が安定するためのシステムをつくることが今、DXと呼ばれ推進されています。
企業だけでなく、人々の生活があらゆる面で革新的に、豊かに、より良い方向へと変化していくために、IT技術を活用していくという取り組みなのです。
結局、デジタル化とDXの区別は難しく曖昧なものではあるのですが、「切符を買わずともICカードで電車への乗車が可能になった」はデジタル化、「モバイルICカードの普及でチャージがスマホから可能であり、電子マネーとしても広範囲で利用できることから現金を持ち歩く必要がなくなった」のはDX、といったところでしょうか。
迫る2025年
2025年問題、2025年の崖、どうやら日本は2025年がひとつの分岐点になるようです。
2025年問題とは、超高齢者社会で生じる影響のことを指します。

そして2025年の崖とは、経済産業省の発表した「DXレポート」で使用された言葉で、DXを推進しないことで低下した業務効率・競争力による経済損失のことを指します。最大で年間12兆円もの損失が予想されており、それまでに経営面、人材面、技術面のいずれにしてもシステム刷新を集中的に推進する必要があります。
とはいえ、従来のシステムを新しくするというのは往々にして腰の重い話です。
コロナ禍で劇的に見直された働き方ですが、それまでテレワークを実施していた企業はどれほどのものだったのでしょうか?
日本でテレワークが推奨され始めたのは2010年後半と言われています。しかし実状は25%を下回る程度しか実施されていませんでした。それがこのコロナのあおりを受け、急速に普及していったのです。
コロナという脅威が目に見えたからこそ、そのメリットが浮き出てきて重たい腰も持ち上がったのでしょう。
現状、2025年の崖という脅威は目に見えているのでしょうか。
AIを利用した業務、自動運転の搭載された自動車、5Gに接続されるスマートフォン。
その一方で、Windows7が2020年にサポートを終了し、来年の頭には8.1のサポートも終了します。
IEも次第にEdgeへと移行されています。
アドビのFlash Playerのサポート終了のときも話題になりましたよね。
技術というものは次から次へと塗り替わっていきます。
…全部知ってるよ!って思いましたか?
では、2025年のIT人材不足は何人まで拡大するでしょうか
PSTN網、INS回線が終了したあとのこと、考えていますか?
サイバー攻撃はどこまで進化するのでしょうか
2025年の崖、ちゃんと見えていますか?
DXへのみち
みんななんだかんだなんとかなると思っています。なんだかんだなんとかなりませんよ。
DXレポートを要約すれば、
・経営層における既存システムの問題点の把握、改善案の不完全
・既存システム刷新の際、各関係者の果たすべき役割の不完全
・既存システム刷新の際、長期にわたり、大きなコストのかかることによるリスク
・ベンダー企業とユーザー企業の関係
・DX人材の不足
以上のことが現状、そして課題として挙げられています。
あー、なんだか面倒だな……なんて気持ちになってきませんか?
現状のままで問題ないし、大丈夫だろ、新しいこと覚えるのも面倒だし。
なーんて、ずるずるあとまわしにして、なんだかんだなんともならないまま2025年が来てしまう。
なんてことにならないように、きちんとDXしていかなければなりません。
しかし、ちゃんと2025年の崖を意識して!と言っても、目に見えないものを意識するのは難しいことです。
それを可視化するのもとても難しいことです。
人材が不足するなんて言われても、じゃあ具体的にどれくらい不足して、どう対処すればいいのかわからないですよね。
では、可視化するために何が一番大事なのでしょうか。
もっとも大事なことは、まず「知ること」です。
何度も繰り返してきましたが、みんななんとなくは認識しています。なんとなく、このままではいけないことはわかる、でもどうすればいいかはわからない。具体的な被害もないし、問題もないから。
ネットで調べれば、DXについての記事やサイトがたくさん出てきます。難しい言葉や知らない単語が出てくるかもしれませんが、わかるところもあるはずです。
わかるところから、わからないところは調べて、そしたらここがわかって、そうやって少しずつ知識を広げていけば、次第に「見えて」きます。
見えてくれば、どうすればいいのかもおのずと見えるようになるのではないでしょうか。
本日のまとめ
変化というのは、そのメリットとそれに適応する億劫さを比べた際に、メリットが勝ることで為されます。
適応するには知識が必要ですし、経験も必要です。
手動だった改札口が自動改札になったときも、切符がICカードになったときも、ICカードがスマホになったときも、はじめこそ戸惑いつつも次第にそれが当たり前になりました。新しいものの知識を付け、受け入れ、そして経験したからこそ便利であると「見えた」からです。
2025年なんてあっという間です。でもまだ間に合いますよ。
知識と経験ほど無駄にならないものもなかなかありませんし、これを機に、漠然とした2025年を知って、見て、DXを推し進めていきませんか。
変化して、適応して、変革されていく。それを繰り返した結果の「いま」です。
次々と変化していくその瞬間にいると考えたら、少しうきうきしちゃいますね。
<参考>